こんにちは。「カロアの自分手帖」管理人のカロアです。
この記事では、中小企業診断士とはどんな資格か? そして、私が受験を決めた理由についてまとめています。
これから試験勉強を始める方や、少し資格に興味がある方、スキルアップしたい方にとって参考になれば幸いです。
中小企業診断士とは?
中小企業診断士は、中小企業の経営課題を分析し、改善のための助言を行う経営コンサルタントの国家資格です。
企業の現状を診断し、財務・人事・マーケティング・生産などあらゆる側面から経営をサポートします。
近年は物価高や人手不足など、中小企業を取り巻く環境は厳しくなっています。
そうした状況で、経営の「ドクター」として専門的に助言できる診断士の存在価値は高まっています。
資格を取得することで、経営企画やコンサルティングなど、企業内外で幅広く活躍できる知識と信頼を得ることができます。
中小企業診断士の主な業務
中小企業診断士の仕事は、大きく次の3つに分けられます。
| 業務内容 | 概要 |
|---|---|
| 経営コンサルティング | 企業の課題を分析し、改善策を提案。経営戦略・財務・人事・マーケティングなど多分野に対応。 |
| 経営診断書・改善計画書の作成 | 金融機関や自治体などに提出する経営診断書・改善計画書を作成。 |
| セミナー・講演・執筆活動 | 経営支援や中小企業政策に関する情報を発信。 |
なお、診断士には弁護士や税理士のような「独占業務」はありません。
その分、自分の強みや興味に合わせて幅広く活動できる自由度の高い資格です。
幅広い仕事を行いたい方、型にはまったことをしたくない方に特にオススメです!
試験の概要
中小企業診断士試験は、以下の3ステップで構成されています。
① 1次試験:基礎知識を幅広く問う
1次試験は7科目から構成され、経済・会計・経営など幅広い知識を問われます。
| 科目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 経済学・経済政策 | 経済全体の動向、金融政策など |
| 財務・会計 | 損益計算書、キャッシュフロー、投資判断など |
| 企業経営理論 | 組織論、人事戦略、マーケティングなど |
| 運営管理 | 生産・品質・店舗管理など |
| 経営法務 | 会社法、知的財産法など |
| 経営情報システム | IT・情報戦略など |
| 中小企業経営・中小企業政策 | 政府支援制度、中小企業の現状 |
- 試験時期:例年8月上旬
- 合格基準:総得点の60%以上(700点満点中420点以上)かつ各科目40点以上
② 2次試験:実践的な思考力を問う
2次試験では、実際の中小企業の事例をもとに経営課題を分析・提案する力が求められます。
- 筆記試験:事例Ⅰ〜Ⅳ(組織・人事、マーケティング、財務、運営)
- 試験時期:例年10月下旬(筆記試験)
- 合格基準:総得点の60%以上、かつ各科目40点以上(2次試験筆記)
③ 実務補習(または実務従事)
試験に合格したら、15日以上の実務補習または実務経験が必要です。
現役の中小企業を実際に診断し、チームで経営改善提案を行う実践的な訓練です。
診断士の先輩から指導を受けながら、実務感覚を身につけます。
資格取得のメリット
① 経営コンサルタントとしての信頼性が高まる
中小企業診断士は、経営分野で唯一の国家資格です。
そのため、企業や金融機関からの信頼性が高く、「専門家」として認知されやすいのが特徴です。
② キャリア・副業・独立の選択肢が広がる
- 企業内でのキャリアアップ(経営企画・事業戦略など)
- 副業としての経営コンサルティング
- 将来的な独立開業
また、他資格とのダブルライセンスにも相性が良く、
社会保険労務士・FP・技術士などと組み合わせて専門領域を拡大できます。
③ 幅広い知識・人脈が得られる
試験範囲が広いため、経営・会計・経済などあらゆる分野の知識が身につきます。
また、診断協会や勉強会・研究会を通じて、志の高い仲間とつながる機会が得られます。
診断士同士のネットワークから、副業や新規事業に発展することも珍しくありません。
私が中小企業診断士を目指そうと思った理由
私がこの資格に挑戦しようと思った理由は、次の3つです。
① 仕事における視野を広げたい
これまで理系資格(電験三種、エネルギー管理士など)を中心に取得してきましたが、
「経営や組織を俯瞰的に理解する力」を身につけたいと思ったのがきっかけです。
経営知識を体系的に学ぶことで、仕事の中でもより広い視野で判断できるようになると感じています。
② 将来的な副業・独立の可能性
診断士資格は副業との親和性が高い資格です。
コンサルティング案件を個人で受ける、セミナー講師として活動するなど、
「自分の知識を収益化できる」点に強い魅力を感じています。
将来的には、理系の専門性と経営知識を掛け合わせた仕事もしていきたいと考えています。
③ ダブルライセンスで専門性を強化
私の場合、理系資格を複数持っているため、文系資格を取得して技術 × 経営の視点を両立したいと考えました。
たとえば「エネルギー管理 × 経営改善」「技術支援 × 経営戦略」といった組み合わせは、
将来的に企業支援の現場で強い武器になるはずです。
勉強の進め方
私は2025年9月から、「スタディング」の通信講座で学習を開始しました。
スキマ時間に動画講義を見られるのが魅力で、仕事との両立にも向いています。
▶ 今後は、実際の勉強法や使用教材、進捗報告なども記事にまとめていく予定です。
まとめ:中小企業診断士は「学び続けたい人」に最適な資格
中小企業診断士は、経営全般を学べる唯一の国家資格です。
取得までの道のりは決して楽なものではありませんが、その過程で得られる知識・人脈・成長は大きな財産になります。
「経営を体系的に学びたい」
「将来の選択肢を広げたい」
「自分の専門性をもっと活かしたい」
そんな方にこそ、中小企業診断士はぴったりの資格です。
私も現在、学習をスタートしたばかりですが、これから少しずつ実体験を発信していく予定です。
一緒に診断士への道を歩んでいきましょう!
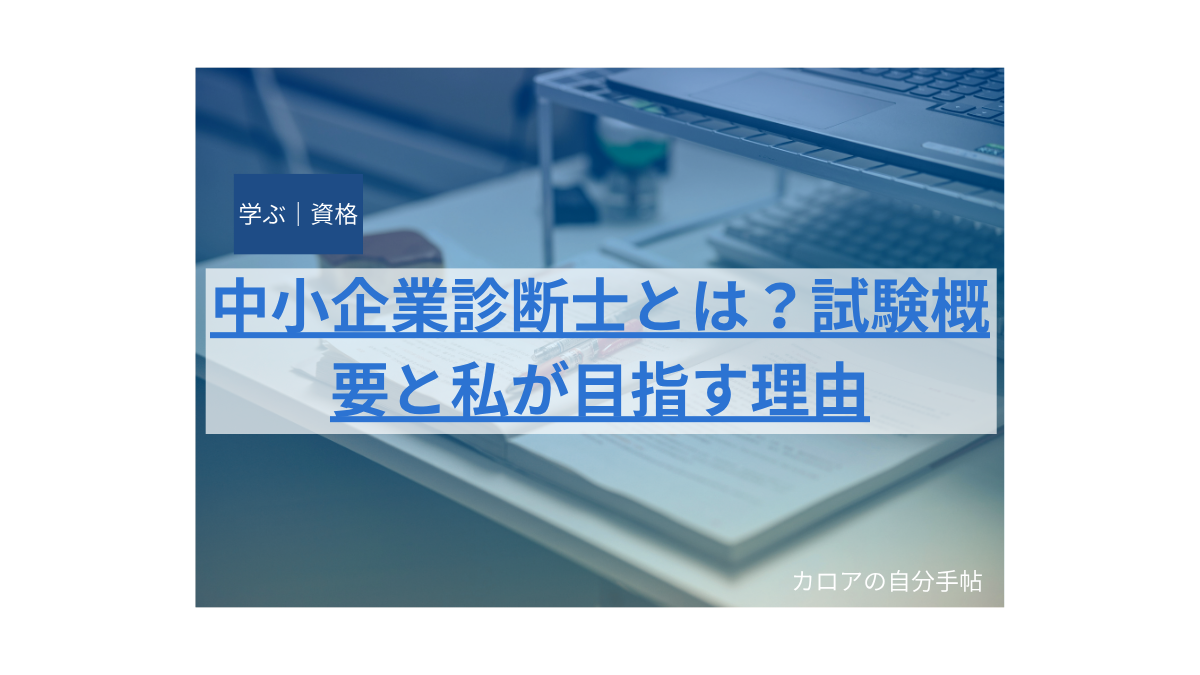
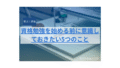
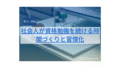
コメント